
高血圧の原因の一つとしてカルシウム不足があるのをご存知ですか。
高血圧をそのままにすると脳卒中などの怖い病気にもつながります。
カルシウムの役割や、なぜカルシウム不足で高血圧となるのか、カルシウム不足を補う食品や一緒に摂りたい成分についてもご紹介します。
日本人はカルシウム不足
日本人の食事摂取基準※1に示されているカルシウムの1日の推奨量は、50〜64歳の男性で750mg、女性で650mgです。
厚生労働省が行った国民健康・栄養調査※2によると、実際には、50歳以上の男性で1日平均471~585mg、女性で472~574mgというカルシウム摂取量という結果で、男女ともに足りていないことが分かりました。
国民・健康調査は毎年行われていますが、カルシウム摂取量は全く増えておらず、平均値が推奨量に達したことがなく、摂取不足が続いています。
カルシウムは骨の健康維持に欠かせないにも関わらず、非常に摂りにくい栄養素なのです。
一日に必要なカルシウムの摂取量とは?
日本人の食事摂取基準※1に示されているカルシウムの1日の推奨量は、50〜64歳の男性で750mg、女性で650mgです。カルシウムは、魚介類、藻類、乳類、豆類、種実類、野菜類に多く含まれていますが、効率的にカルシウムを摂取するのには牛乳や乳製品が最適といわれています。牛乳・乳製品を中心に、小魚、海藻、豆類、野菜などの食品からバランスよく摂りましょう。
<含まれるカルシウム量>
可食部100gあたりのカルシウム量※3
- 普通の牛乳 (100mlあたり 約100g)・・・ 110mg
- ヨーグルト(無脂肪無糖)(100g)・・・ 140mg
- しらす干し(半乾燥品)(大さじ約20杯)・・・ 520mg
- 糸引き納豆 (1パック50gとした場合、2パック)・・・90mg
- 小松菜 葉(生)(約3株程度)・・・ 170mg
カルシウムの役割とは?
体内には、おおよそ1㎏のカルシウムが存在し、その99%が骨と歯に存在しています。
それ以外にある残りの1%は血液中や細胞などに存在しています。
そして、カルシウムには、大きく2つの重要な役割があります。
1. 骨の硬さを維持し、体を支えること
骨は約3ヶ月のサイクルで、骨形成(骨へのカルシウムなどの沈着)と骨吸収(骨からのカルシウムなどの溶出)を繰り返しています。
成長期には形成量のほうが吸収量より多く、骨量は増加します。
しかし、男性では50歳代から、女性では閉経後に、吸収量のほうが形成量を上回るため骨量が減少してしまい、注意が必要です。
2. 「生命を維持する」という役割
ほとんどは骨や歯に存在しているカルシウムですが、残りの1%も大切な役割をしています。
主に、血液や筋肉などの組織にあり、出血を止める働きや、神経の情報伝達、筋肉運動など、生命を維持する役割をしています。
この1%のカルシウムが、血液中で一定の濃度に保たれることで、身体のさまざまな機能が正常に働くよう調整されているんです。
血液中には常に同じだけのカルシウム量が必要なので、足りない場合は、骨は自らを壊してカルシウムを補います。
骨は実はカルシウムの貯蔵庫としての役割もあるのです。
カルシウムを取りすぎても大丈夫?
1. カルシウムの摂取上限は2,500mg
2. カルシウムは日本人が不足している栄養素
どの栄養素においても、過剰に摂り過ぎたり、少なすぎたりするのは、良くありませんよね。
カルシウムの摂取上限は、2500mgとされています。
これは、これ以上摂ると健康障害の危険性があり、ここまでは近づかない方が良いという“耐容上限量”という目安によるものです※4。
カルシウム2500mgとは牛乳に換算すると1日2リットル以上です。
牛乳パック約2本以上を毎日飲む人はほとんどいないと思いますが、実際にカルシウムを摂り過ぎて、高カルシウム血症(血液中カルシウム濃度が上がりすぎる)が起こった例では、1日3,000mg以上に限られているため、摂取上限では、安全を見越して2,500mgとなっています。
カルシウムは、日本人の多くが不足している栄養素なので、過剰摂取の心配をするより、積極的摂取を心がけるべき栄養素なのです。
カルシウムパラドックスとは
パラドックスとは「逆説」を意味する言葉ですが、「カルシウムパラドックス」とはどんな状態なのでしょうか?
丈夫な骨や歯のためにカルシウムを十分に摂ることは大切ですよね。
カルシウム摂取が不足すると、骨折しやすくなったり骨粗しょう症を引き起こす原因にもつながります。
しかし摂取不足が原因で、血液中に余分なカルシウムが増えすぎることがあるのです。
これが「カルシウムパラドックス」です。
このカルシウムパラドックス現象はどうして起きるのかというと、人間の身体の中のカルシウムは99%が骨や歯に存在していますが、残りの1%は血液中や細胞などに存在しており、私たちの身体は、この残り1%の血液中のカルシウム濃度を常に一定に保つようにできているからなのです。
カルシウムの摂取が不足して“血液中のカルシウムが減少”すると、副甲状腺ホルモンが分泌され、骨からカルシウムを取り出すように働きかけます。
これは一時的にカルシウムが不足しても、骨から溶け出したカルシウムで、血液中のカルシウム濃度を保つための身体の防衛の仕組みなのです。
しかし、慢性的に不足してしまうと、副甲状腺ホルモンが常に分泌されている状態になり、その結果、骨から過剰にカルシウムが溶かしだされることになり、余分になったカルシウムが身体のさまざまな部位に溜まってしまうのです。
<カルシウムパラドックスが引き起こす問題>
カルシウムパラドックスによって、骨から過剰に溶かしだされたカルシウムが血管壁に溜まると、動脈硬化や高血圧を引き起こしやすくなります。
またカルシウムが尿路でシュウ酸やリン酸などと結びつくことによって尿路結石にもつながります。
骨から過剰にカルシウムが取り出されることで、骨がスカスカになり、骨粗しょう症の原因ともなってしまうため、非常に怖いですよね。
こうしたさまざまな生活習慣病などの原因となるカルシウムパラドックスは、カルシウムの摂取不足によって起こるということがポイントです。
日本人にとって摂取が不足がちな栄養素と言われるカルシウムですが、日々の食事などから毎日しっかりと摂取するように意識しましょう。
カルシウム不足と高血圧の関係
カルシウム不足は、骨折や骨粗しょう症の原因となることを知っている方は多いと思いますが、
カルシウムパラドックスにより、カルシウム不足が“高血圧”や“動脈硬化”などの原因になることもわかりました。
カルシウムの働きは骨の形成だけではなく、血管などの細胞の活動にも大きな影響を与えています。
そのためカルシウムが不足すると、血圧の上昇や血管の老化を招きやすく、高血圧や動脈硬化にもつながってしまう可能性があるのです。
特に高血圧は、約4300万人の患者がいると推定され、実に日本人の1/3※5が当てはまるといわれるほど身近な病気です。
さらに自覚症状があまりないため、気がつかずに進行している人も多いと言われています。
「高血圧」とは安静状態での血圧が“慢性的に正常値よりも高い状態”をいいます。
高血圧になると、常に血管に負担がかかった状態となり、血管の内壁が傷ついたり、柔軟性がなくなり固くなったりして、動脈硬化を起こしやすく、放置すると、脳卒中や心筋梗塞、腎臓病などの重大な病気につながる可能性があります。
実はとても身近な病気であることを知っておきましょう。
カルシウムはどんな食品から取ればいい?
実は、カルシウムが豊富に含まれている食品は、かなり限られており、吸収率も食品ごとに異なります。
せっかくカルシウムをたくさん摂っても吸収されなかったら困りますよね。
女子栄養大学の上西一弘先生による、非常に厳密な方法で調べられた結果によると、カルシウム吸収率は、牛乳で約40%、小魚で約33%、野菜で19%※6でした。
カルシウムを食品から摂取するのであれば、吸収率を考えて、まずは乳製品、次いで小魚がオススメです。
効率的に摂取できるサプリメントなどもオススメです。
カルシウムと一緒に摂りたい成分 マグネシウム
カルシウムとマグネシウムには深い関わりがあることがわかりました。
カルシウムとマグネシウムはバランスが大切で、マグネシウム1に対して、カルシウム2の割合が人体にとって理想的であると言われています。
この理想的なバランスが保たれていると、心臓や血管などの機能を正常に保ちます。カルシウムだけを摂るよりも、マグネシウムも一緒にバランスよく摂取することが大切です。
マグネシウム自体も人間の骨や筋肉中に存在するミネラルで、体内で300種類以上もの酵素の働きを助け、ほとんどの生合成や代謝に必要となる重要な成分です。
マグネシウムは通常の食事から摂取できますが、睡眠不足や運動不足、ストレスが多い時などは、体内のマグネシウムが消費されやすいため、不足しがちになります。
カルシウムとマグネシウムのバランスを考えたサプリメントなどで補給するのもオススメです。
カルシウムと一緒に摂りたい成分 ビタミンD
カルシウムを助ける重要な栄養素にビタミンDがあります。
ビタミンDは体の中で、様々な役割をしていますが、最も重要なのは、カルシウムの腸からの吸収を助ける役割と言われています。
例えば、骨が“高層ビル”だとすると、鉄筋の枠組み+コンクリートでビルができるように、骨はコラーゲンを中心としたタンパク質の枠組みの上に、リン酸カルシウムが沈着してできています。
しかし、ビタミンDが欠乏すると、せっかく摂ったカルシウムが十分吸収できず、カルシウムが沈着できないのです。これが子どもの時に起こったものをクル病といい、成人で起こったのを骨軟化症といいます。
本来ビタミンは体内で合成できず、食事から摂取すべき栄養素なのですが、実は、ビタミンDは紫外線があたると皮膚でかなりの量ができるんです。
カルシウムを十分摂った上で、適度の屋外活動をすることは、骨の健康維持に重要です。
まとめ
いかがでしたか。
カルシウムを摂取して、骨を丈夫にすることは、健康に生きていくうえでとても大切ですよね。
また、骨の形成だけではなく、カルシウムは生命維持のためには欠かせない成分であり、カルシウムが慢性的に不足してしまうと、骨からカルシウムが溶け出してしまい、逆に血中に溶け出したカルシウムが増えてしまうこともわかりました。
その結果、動脈硬化や高血圧の原因にもつながるので、日頃から積極的にカルシウム摂取を心がけていきたいですね。
カルシウム吸収率の良い乳製品や小魚、また効率的に摂取できるサプリメントなどもあるので、続けやすい方法を見つけてみましょう。
参考文献:※1 日本人の食事摂取基準(2020 年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書
令和元年12月. 「日本人の食事摂取基準」策定検討会
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)より P308
参考文献:※2 令和元年国民健康・栄養調査報告 厚生労働省 令和2年12月. 第1部 栄養素等摂取状況調査の結果 より P70-74
参考文献:※3
文部科学省 食品成分データベース
参考文献:※4 日本人の食事摂取基準(2020 年版)「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書
令和元年12月. 「日本人の食事摂取基準」策定検討会
カルシウムの食事摂取基準(mg/日)より P308
参考文献:オムロン ヘルスケア株式会社 健康コラム はじめよう!ヘルシーライフ vol.15 カルシウム不足を解消して高血圧や動脈硬化を予防するより
参考文献:※5 オムロン ヘルスケア株式会社 ゼロイベント 高血圧による脳・心血管疾患の発症ゼロへ 血圧ラボ 血圧基礎知識編 血圧データベース日本の高血圧人口(有症者数)
参考文献:※6 一般社団法人 Jミルク 知っていますか?カルシウムの”吸収率”のこと 40%ものカルシウムを吸収 できる、牛乳の栄養バランスより
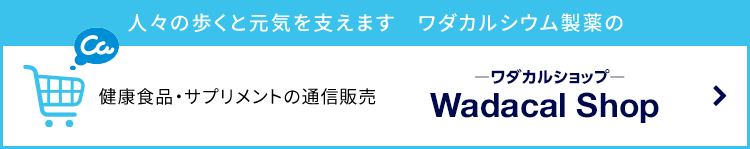
関連コンテンツ
-
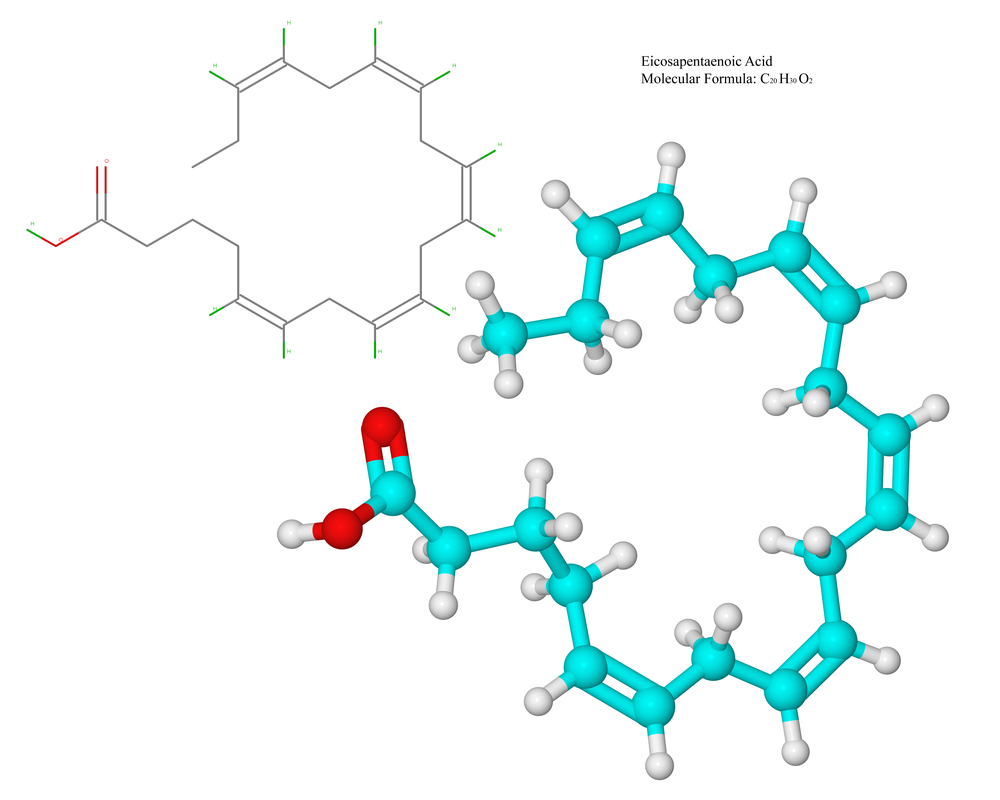 健康コラム
健康コラム「オメガ3脂肪酸」で身体の中からアンチエイジング!
2019.06.04 最近物覚えが悪くなった、健康のために生活習慣を見直したい…… 年齢に伴ってこうした悩みを意識し始めた、という方は多いのではないでしょうか? そんな方にご紹介した […]
- DHA
- 生活習慣病
-
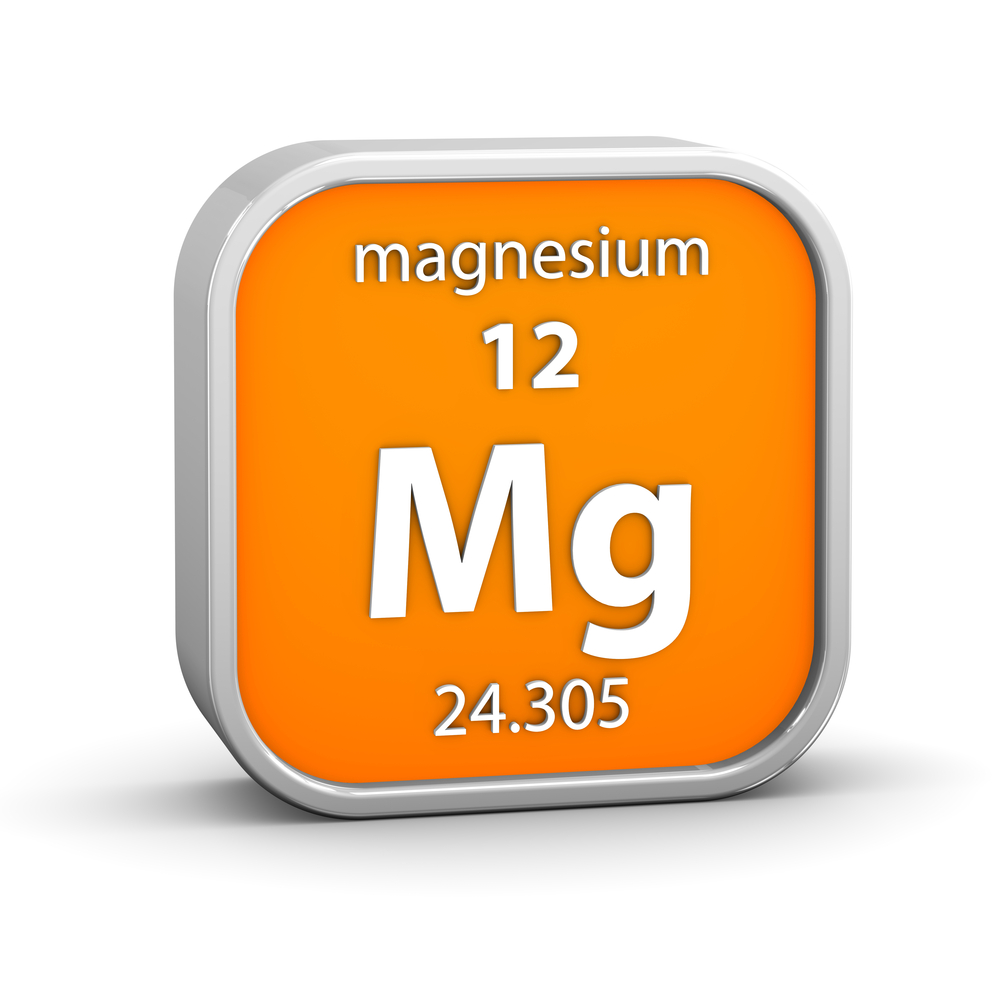 健康コラム
健康コラムカルシウムと深い関係!ご存じですか?「マグネシウム」の効果
2019.06.04 「マグネシウム」と聞くと何が思い浮かぶでしょう。理科の実験や花火に使われる金属、 という印象を持っている方も多いかもしれませんね。 マグネシウムは、人体 […]
- カルシウム
-
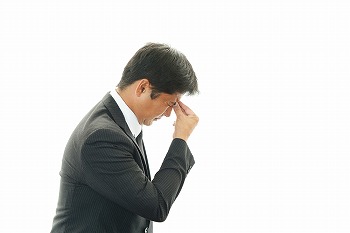 健康コラム
健康コラム脳機能低下の抑制が期待される「オメガ3系脂肪酸」が凄い!
2019.06.03 高齢化社会が進み、認知症などの脳機能の低下が課題になっています。 そんな社会情勢の中、今「オメガ3系脂肪酸」の脳に対する機能性が注目されていることはご存知でし […]
- DHA
- 記憶力低下
人気のコラム
-
 健康コラム
健康コラム朝にコップ一杯の水を飲んでキレイになりましょう !
2019.06.03 女優やモデルさんの中には美容と健康の秘訣を「寝起きにコップ1杯の水を飲む」と答える人が多くいます。 この「朝にコップ1杯の水を飲む」美容法は有名なものです […]
- ダイエット
- 便秘
- 便通
- 寝起きに飲む一杯の水
- 朝コップ一杯の水
- 水を飲むメリット
- ダイエット
- 便秘
- 水
-
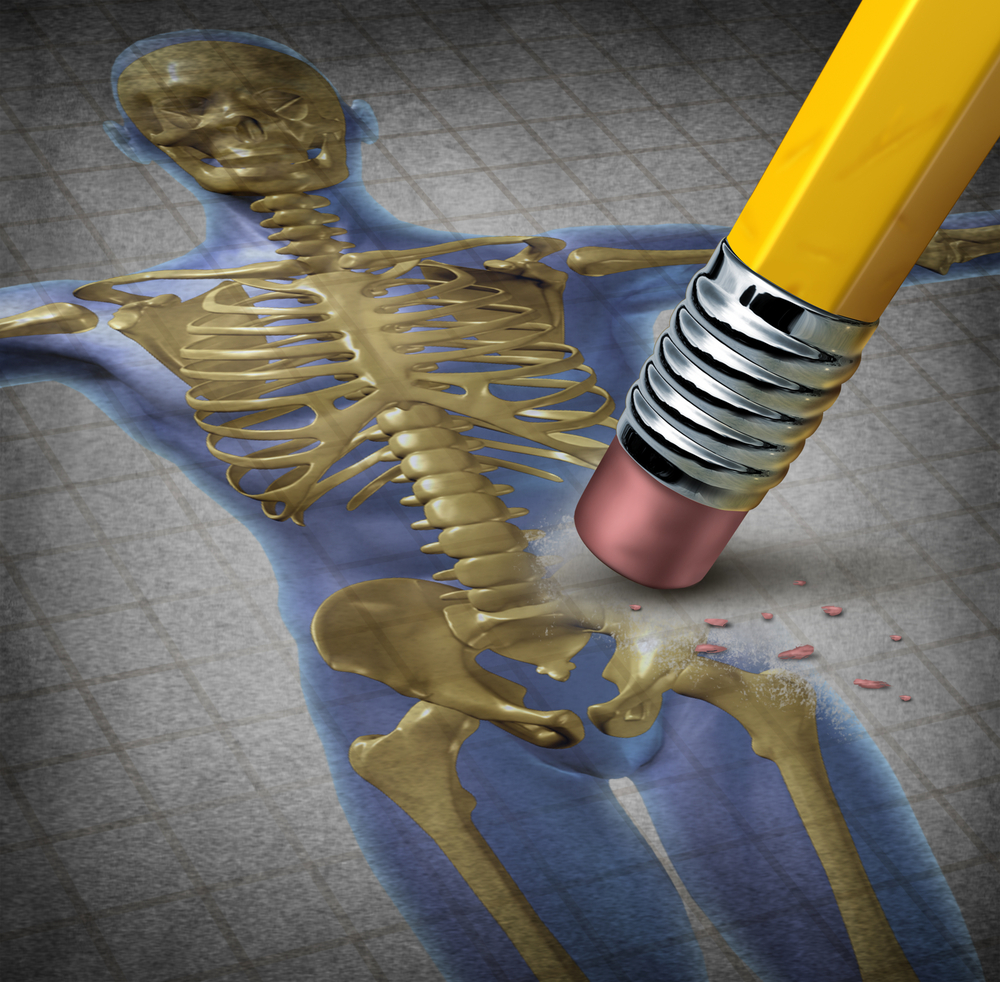 骨活応援 by ワダカルシウム製薬
骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨粗しょう症に繋がる「骨密度・骨量」が低下する原因とは
2019.06.03 骨の強さはほとんど骨密度で決まります。その骨密度が低下することによって 骨が脆弱になってしまい、骨粗しょう症の原因になります。 高齢な方がかかりやすい病気で […]
- カルシウム
- ビタミンD
- 骨
- 骨粗しょう症
-
 健康コラム
健康コラム将来が怖い!?「カルシウム不足」が招く○○症の脅威!!
2019.06.03 カルシウム不足 カルシウム不足によって、何が起きるでしょうか。 これから成長する世代だと、成長が止まってしまうなど、骨の形成に障害が出ることがあります。 […]
- カルシウム
- ビタミンD
- カルシウム不足
- 骨粗しょう症
-
 骨活応援 by ワダカルシウム製薬
骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨折や骨粗しょう症予防のために「始めよう、骨に良い食事」
2019.06.03 骨量が減り、骨がスカスカになってしまう病気、骨粗しょう症。 老人の病気だと考えられがちですが、ダイエットなどの影響で、若い女性にも骨粗しょう症 予備軍は増え […]
- カルシウム
- 骨粗しょう症
-
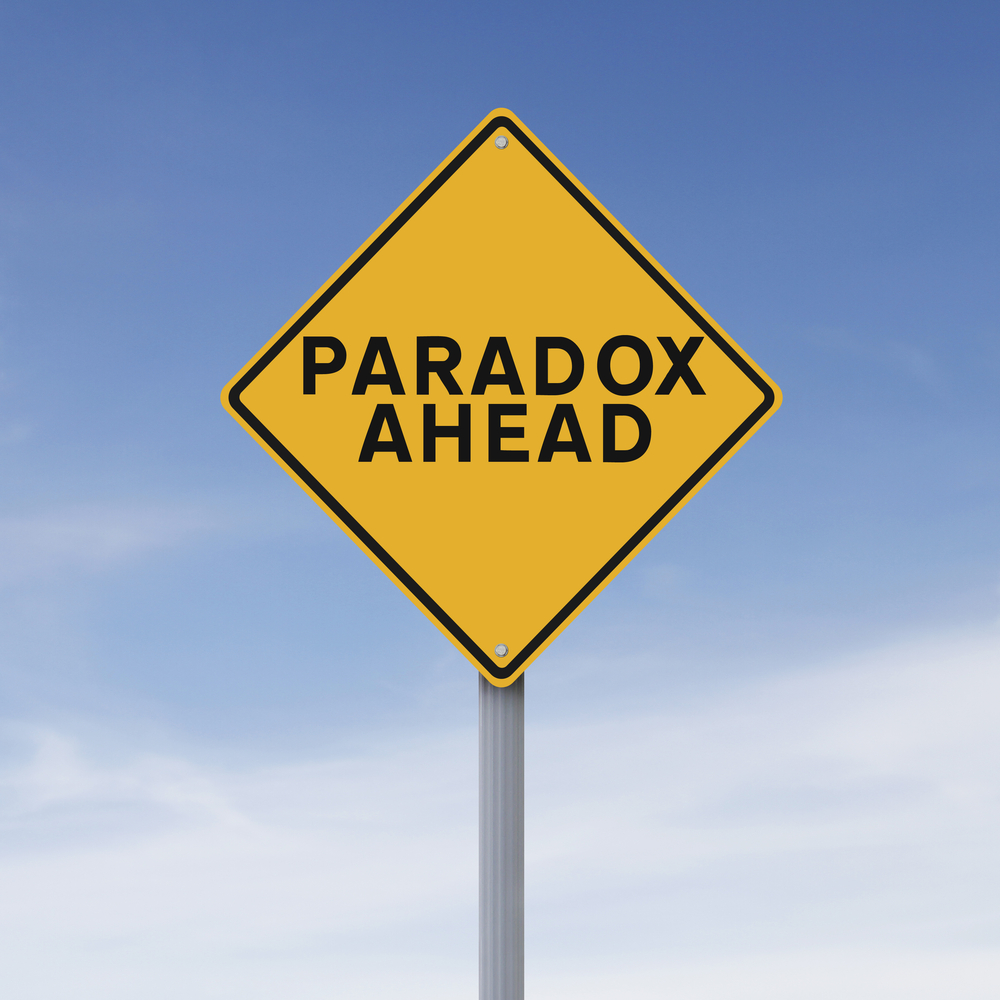 健康コラム
健康コラム摂取不足が余分を生み出す「カルシウムパラドックス」とは
2019.06.03 丈夫な骨や歯のためにカルシウムを十分に摂ることは欠かせません。 カルシウムの摂取が不足すると、骨折しやすくなったり骨粗しょう症を引き起こす原因 となったりし […]
- カルシウム
- 骨粗しょう症


