目次
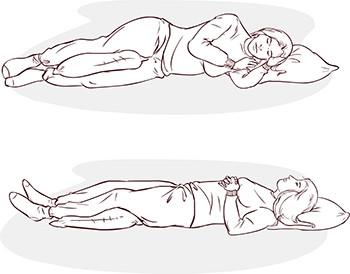
仰向け寝、うつぶせ寝、横向き寝のメリットデメリット
健康維持にとって、睡眠はとても重要。
うつぶせ・仰向け・横向きなど様々な寝方がありますが、それぞれのメリットやデメリットについてご紹介いたします。
仰向け寝
仰向け寝とは、背中側を布団につけた姿勢で、天井側を見て寝ることです。
仰向け寝メリット
仰向け寝には様々なメリットがあります。
理想的な寝姿勢に近い
理想的な寝姿勢は、人がまっすぐに立っている時の“なだらかなS字状にカーブした背骨”の状態を保つことと言われています。
仰向け寝の姿勢は、体をひねる動作がないため、自然と背骨がまっすぐな状態となりやすく、普段、背中が丸まりがちで猫背の人も、仰向けに寝ることで背骨をまっすぐに伸ばすことができオススメです。
仰向け寝メリット
仰向け寝には様々なメリットがあります。

理想的な寝姿勢に近い
理想的な寝姿勢は、人がまっすぐに立っている時の“なだらかなS字状にカーブした背骨”の状態を保つことと言われています。
仰向け寝の姿勢は、体をひねる動作がないため、自然と背骨がまっすぐな状態となりやすく、普段、背中が丸まりがちで猫背の人も、仰向けに寝ることで背骨をまっすぐに伸ばすことができオススメです。
体にかかる圧が分散され、負担がかかりにくい
体が敷布団と接している面積が広いため、体にかかる圧が均等に分散され、局所的に圧迫される事が少なく、体へ負荷がかかりにくいと言われています。
寝ている間に首や肩などへの負担がかからず、起床時に体が痛みにくいというメリットがあります。
血液が循環しやすくなり、疲労回復を助ける
圧迫される事が少ないため、全身に血液が循環しやすいと言われています。
血液が循環することで、疲労回復を助けることができます。
寝返りをしやすい
寝返りは快適な睡眠のためには欠かせません。
仰向け寝は、安定した姿勢のため、寝返りを打ちやすと言われています。
体にかかる圧が分散され、負担がかかりにくい
体が敷布団と接している面積が広いため、体にかかる圧が均等に分散され、局所的に圧迫される事が少なく、体へ負荷がかかりにくいと言われています。
寝ている間に首や肩などへの負担がかからず、起床時に体が痛みにくいというメリットがあります。
血液が循環しやすくなり、疲労回復を助ける
圧迫される事が少ないため、全身に血液が循環しやすいと言われています。
血液が循環することで、疲労回復を助けることができます。
寝返りをしやすい
寝返りは快適な睡眠のためには欠かせません。
仰向け寝は、安定した姿勢のため、寝返りを打ちやすと言われています。
仰向け寝デメリット
たくさんのメリットのある仰向け寝ですが、デメリットもあります。
仰向け寝では、“いびき”をかきやすくなると言われています。
寝ている時は、全身の筋肉がゆるみ、舌を含む喉の周りの筋肉も緩みます。
仰向けに寝ると重力の影響で舌が喉の奥に落ち込み、気道が狭くなり、その狭い気道に空気が通ると、周りの組織が振動して“いびき”が起こるのです。
(対処法)
“いびき”が気になる方は、気道がふさがるのを防ぐ「うつぶせ寝」や「横向き寝」がオススメです。
ただし、寝返りすることが難しい赤ちゃんや高齢者の方、妊婦の方などは注意が必要です。
うつぶせ寝
うつぶせ寝とは、お腹側を下にして、身体の前面を布団につけた姿勢で寝ることです。
一見苦しそうに見えるうつぶせ寝ですが、実はメリットもたくさんあります。
うつぶせ寝メリット
うつぶせ寝には、様々なメリットがあると言われています。
腹式呼吸ができる
うつぶせ寝は胸が圧迫されるため「呼吸がしにくい?」と思うかもしれませんが、実はうつぶせの姿勢は、胸を使った「胸式呼吸」が抑えられ、自然と横隔膜が動き、より深い「腹式呼吸」ができるというメリットがあります。
呼吸が楽になる
寝ている時は筋肉が緩み、舌の付け根が重力により喉におち、気道が狭くなります。しかしうつぶせ寝は、空気の通り道である気道が確保されるため、呼吸がしやすい状態となり、熟睡しやすい姿勢と言えます。
いびきを防ぐ
気道が確保されているため、“いびき”をかきにくい体勢となります。
血行不良の改善
呼吸がしやすいため、血液中に十分な酸素が届き、血行不良になりにくいと言われています。
疲労蓄積や老化の予防
呼吸がしやすいため、血液中に十分な酸素が行き渡り、血中酸素不足による疲労回復の遅れや、老化の予防が期待できます。
うつぶせ寝デメリット
たくさんのメリットのあるうつぶせ寝ですが、デメリットもあります。
うつぶせ寝では、胸部に負担がかかるため、腰痛を始めとして全身の骨格の歪みや、O脚、女性の胸の型崩れの原因になる可能性があります。
さらにうつぶせ寝は、顎関節症や歯並びにも悪影響を及ぼす可能性があると考えられています。
体に負担がかかっているなと感じたら、症状にあった対処をするようにしましょう。
うつぶせ寝の呼吸
うつぶせ寝では自然と腹式呼吸になるというメリットがありますが、実は寝る直前の行動が呼吸法に影響を及ぼすこともあるので注意が必要です。
例えば、夜遅くまで仕事をしたり、スマートフォンやパソコンなどを見たりすることで、「交感神経」が優位になります。
この状態で眠りにつくと、スムーズに腹式呼吸に切り替わることができず、胸式呼吸のままの状態になってしまうのです。
うつぶせ寝では胸を圧迫しているため、胸式呼吸がしにくく、眠りを妨げてしまいます。
質の良い睡眠のためには、寝る前は、できるだけリラックスし、スマートフォンなどは布団に持ち込まず、ゆったり眠りにつくといいでしょう。
赤ちゃんのうつぶせ寝は要注意
赤ちゃんは自分自身で寝返りを上手にできず、うつぶせ寝をすることにより、布団や枕で口がふさがれ、呼吸ができず、窒息する危険性があるため、注意が必要です。
また、うつぶせ寝は「乳幼児突然死症候群」(SIDS=Sudden Infant Death Syndrome)のリスクを高める危険性があるとも言われています。
乳幼児突然死症候群とは、なんの病気もなく元気だった赤ちゃんが睡眠中に突然亡くなってしまう病気で、窒息などの事故死は含まれていません。
うつぶせ寝、あおむけ寝のどちらでも発症しますが、うつぶせ寝の方が発生率が高いということが研究者の調査で分かっています。
1歳頃までは、赤ちゃんの顔が見える仰向け寝をさせてあげましょう。
横向き寝
横向き寝は、体全体で横向いて寝る姿勢です。またお布団の中に丸まって寝る場合も、同じようなメリットやデメリットが考えられます。
横向き寝のメリット
いびきを防ぐ
“いびき”を防ぐために効果的と言われています。
寝返りがしやすい
横向き寝は、寝返りがしやすいと言われています。血液もバランス良く循環するというメリットがあります。
横向き寝のデメリット
横向き寝は、片側の肩や骨盤に、より大きな負担がかかってしまうため、同じ側を下にして寝続けると体の歪みが生じてきます。
特に肩が内側に入ったり、足を組んだ状態となり、歪みが生じやすくなるので気をつけましょう。
また、顔の側面が枕やマットと擦れてしまうので、顔のたるみやほうれい線などのシワができやすくなるので、気をつけましょう。
こんな不調にオススメの寝方
寝る姿勢を変えることで、体の不調を楽にすることもできます。
(1)腰痛がある
横向き寝で、足の間にクッションなどを挟み、足と腰の高さが水平になるようにすると、腰の痛みが緩和されます。
体を少し丸めて横になるのもいいですよ。
(2)いびきがある・息苦しい
いびきがある場合は、仰向け寝ではなく、気道が確保しやすい、横向き寝、うつぶせ寝がいいでしょう。
これらは呼吸が楽になる寝姿勢でもあります。
仰向けで寝たい場合は、大きめの枕などで頭の位置を上げて、膝を曲げた状態にすると呼吸がしやすくなります。
(2)胃酸が逆流する
横に寝転ぶと重力の関係で、胃の内容物が食道に逆流しやすくなってしまいます。
その際右を下にして横になると余計逆流しやすくなると言われています。
枕を少し高くしたり、ベッドを少し起こして頭を高くして寝る姿勢が、胃酸逆流の症状の改善には良いとされています。
寝返りについて
寝る時の姿勢も大切ですが、実は、良い睡眠にするには、寝るときの姿勢よりも、寝返りをスムーズに行うことの方が大事なんです。
寝返りは、体温の調節や、体重圧を分散し、圧迫され続けることを防ぎ、体をほぐすなどの働きがあります。
寝ている時の体の負担を和らげ、体温や湿度を調整し、快適な睡眠にしてくれているのです。
人間の睡眠は、深い眠り(ノンレム睡眠)と浅い眠り(レム睡眠)を繰り返していますが、寝返りは、深い眠りから浅い眠りに変わる時によく起こります。
寝返りには、レム睡眠とノンレム睡眠を切り替えるスイッチの役割があると言われており、睡眠のリズムが一定であると良い睡眠を得ることができ、しっかり体と脳を休ませてあげることができるのです。
<寝返りをしやすくする方法>
まずは睡眠環境を整えてみましょう。
・やわらかすぎる布団・マットレスは、体が沈み込み寝返りがしにくいため気をつけましょう。
・掛け布団や毛布は重すぎないものを選びましょう。
・首や背中に負担のかからない枕を選びましょう。
・動きやすく、体に負担のかからないようなパジャマを選びましょう。
睡眠時無呼吸症候群とは?
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時に呼吸が止まってしまう病気です。
肥満の人、や急に太ってしまった人などは、発症のリスクが高まります。
睡眠中に呼吸が止まると血液中の酸素濃度が低下するため、目が覚めて再び呼吸し始めますが、眠るとまた止まってしまい、睡眠が分断されてしまいます。
呼吸をしていない時間が長くなると命に関わる危険性もあります。
また、睡眠時無呼吸症候群では、高血圧や動脈硬化、心筋梗塞や脳梗塞のリスクも高まるため注意が必要です。
激しい“いびき”や、睡眠中に呼吸が止まることがある場合には、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
睡眠時の環境を整えることも大切
寝る時の姿勢や、寝返りのしやすさを心がけることで、もっと快適な睡眠時間を手に入れることができますが、睡眠時の環境を整えてあげることも、とても大切です。
*部屋は暗くしましょう
光を浴びると脳が活性化され、体内時計にも影響してしまうため、できるだけ部屋は暗くするようにしましょう。
*テレビやラジオは消しましょう
寝る前に音楽などを聞くことはいいのですが、寝ている間は、静かな状態の方が良いとされています。テレビやラジオはつけっぱなしにせずに寝ましょう。
*過ごしやすい温度にしましょう
夏場は約25-26度、冬場は約22−23度で、湿度は50−60%が理想的と言われています。
特に夏場は、熱中症なども気になるため、過ごしやすい温度環境で寝ましょう。
*枕の高さ
特に枕選びは重要だと言われています。ゆるやかなS字を描く首筋の隙間を埋めるような枕を選ぶようにしましょう。
高すぎても低すぎてもよくないため、ご自身に合う枕を選ぶことが大切です。
*寝る前は、スマートフォンなどを見ない
脳を活性化させてしまうため、寝る前は、できるだけスマートフォンなどを見ないようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか。睡眠は人間にとって欠かすことができない大切な時間です。
快適な睡眠にすることで、疲労回復や、美容にも健康にもいいことがたくさんあります。
せっかく同じ時間寝るのであれば、効果的な睡眠時間にしたいですよね。
寝る姿勢や、寝返りのしやすさ、寝る環境などを整えながら、気持ちの良い睡眠がとれますように。
参考文献:ベストな寝る姿勢は「仰向け」?「横向き」?悩み別のおすすめの寝姿勢もご紹介
参考文献:サワイ健康推進課 怖い病気が隠れていることも いびき
参考文献:幻冬舎 「正しい腹式呼吸」ができているか——自分自身で確認する方法
参考文献:厚生労働省 乳幼児突然死症候群(SIDS)について 睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう (1) 1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう
参考文献:ペンギンこどもクリニック 乳幼児突然死症候群(SIDS)について
参考文献:フランスベッド 理想の寝姿勢って?
参考文献:NHK健康 おうちで学ぼう 病気・健康 Q&A 【Q&A】寝るときの姿勢は?胃食道逆流症(逆流性食道炎)
参考文献:日本消化器病学会ガイドライン 胃食道逆流症(GERD)ガイドQ&A
参考文献:Domani 働く40代は、明日も楽しい! なぜ子どもは寝相が悪いの?【教えて!チコちゃん】
参考文献:フランスベッド よくある質問 快眠のポイント 寝返りをする意味やメリットとは?寝返りをしやすくして快適な睡眠を手に入れよう
参考文献:e-ヘルスネット 睡眠時無呼吸症候群(すいみんじむこきゅうしょうこうぐん)
参考文献:西川 日本睡眠科学研究所 「良い睡眠」の秘密
良い睡眠の条件
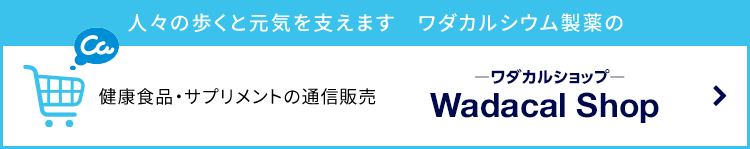
関連コンテンツ
-
 健康レシピ
健康レシピ健康レシピ 19 癒しのマロンプリン
2020.02.13 癒しのマロンプリン ~GABAでリラックス~ 材料(2人分) 甘栗 10個(50g) 牛乳 71.4ml( […]
- 睡眠
-
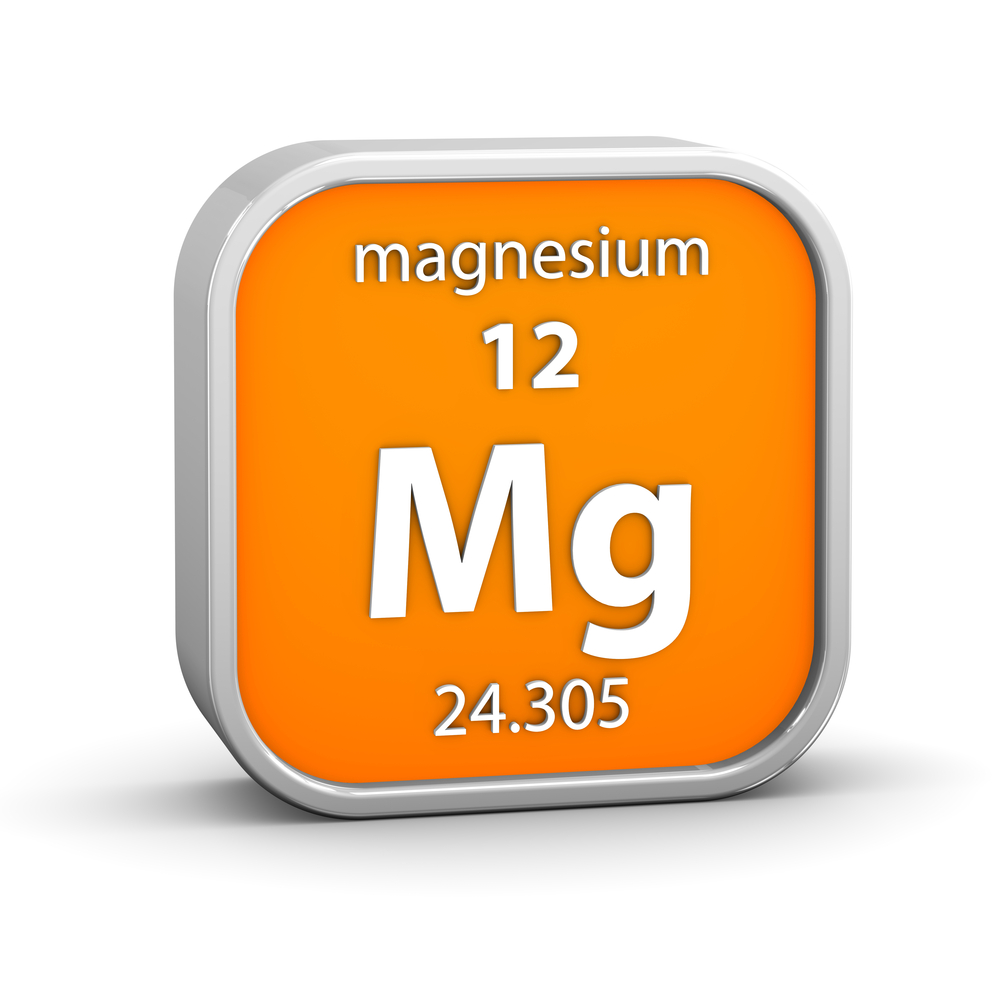 健康コラム
健康コラムカルシウムと深い関係!ご存じですか?「マグネシウム」の効果
2019.06.04 「マグネシウム」と聞くと何が思い浮かぶでしょう。理科の実験や花火に使われる金属、 という印象を持っている方も多いかもしれませんね。 マグネシウムは、人体 […]
- カルシウム
-
 健康コラム
健康コラム意外にカンタン!? 生活リズムを整える習慣
2019.06.03 「美容・健康には生活リズムを整える事が大事!」とよく耳にしますが、生活リズムとは どのようにして整えるのでしょうか? 無理に生活リズムを整えようとすると […]
- カルシウム
- 睡眠
人気のコラム
-
 健康コラム
健康コラム朝にコップ一杯の水を飲んでキレイになりましょう !
2019.06.03 女優やモデルさんの中には美容と健康の秘訣を「寝起きにコップ1杯の水を飲む」と答える人が多くいます。 この「朝にコップ1杯の水を飲む」美容法は有名なものです […]
- ダイエット
- 便秘
- 便通
- 寝起きに飲む一杯の水
- 朝コップ一杯の水
- 水を飲むメリット
- ダイエット
- 便秘
- 水
-
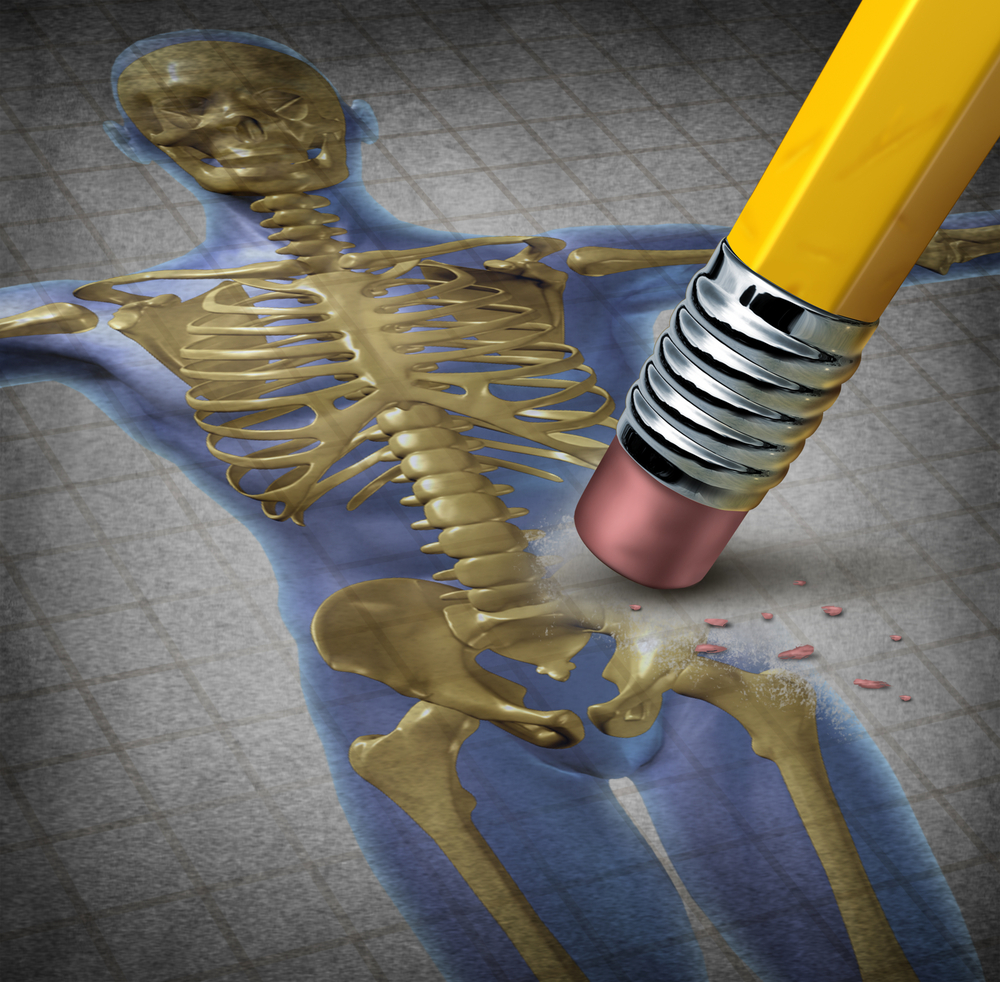 骨活応援 by ワダカルシウム製薬
骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨粗しょう症に繋がる「骨密度・骨量」が低下する原因とは
2019.06.03 骨の強さはほとんど骨密度で決まります。その骨密度が低下することによって 骨が脆弱になってしまい、骨粗しょう症の原因になります。 高齢な方がかかりやすい病気で […]
- カルシウム
- ビタミンD
- 骨
- 骨粗しょう症
-
 健康コラム
健康コラム将来が怖い!?「カルシウム不足」が招く○○症の脅威!!
2019.06.03 カルシウム不足 カルシウム不足によって、何が起きるでしょうか。 これから成長する世代だと、成長が止まってしまうなど、骨の形成に障害が出ることがあります。 […]
- カルシウム
- ビタミンD
- カルシウム不足
- 骨粗しょう症
-
 骨活応援 by ワダカルシウム製薬
骨活応援 by ワダカルシウム製薬骨折や骨粗しょう症予防のために「始めよう、骨に良い食事」
2019.06.03 骨量が減り、骨がスカスカになってしまう病気、骨粗しょう症。 老人の病気だと考えられがちですが、ダイエットなどの影響で、若い女性にも骨粗しょう症 予備軍は増え […]
- カルシウム
- 骨粗しょう症
-
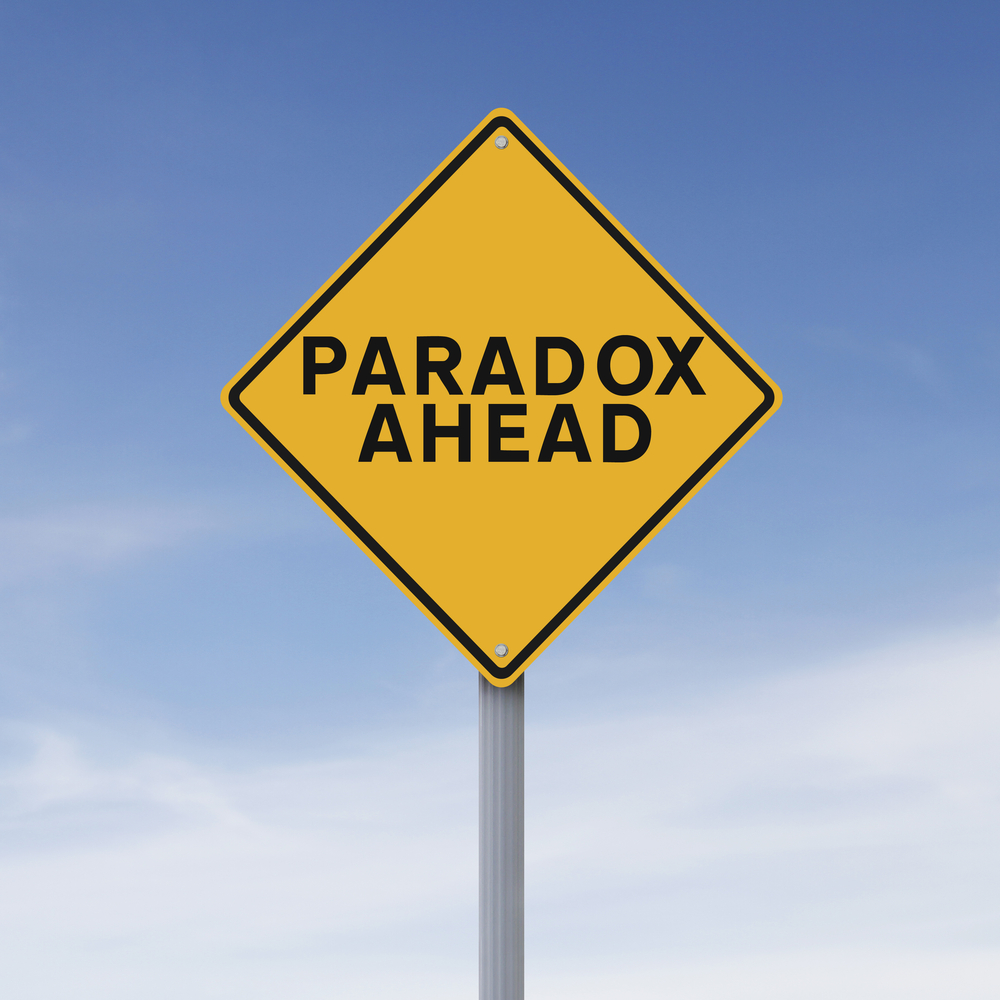 健康コラム
健康コラム摂取不足が余分を生み出す「カルシウムパラドックス」とは
2019.06.03 丈夫な骨や歯のためにカルシウムを十分に摂ることは欠かせません。 カルシウムの摂取が不足すると、骨折しやすくなったり骨粗しょう症を引き起こす原因 となったりし […]
- カルシウム
- 骨粗しょう症


